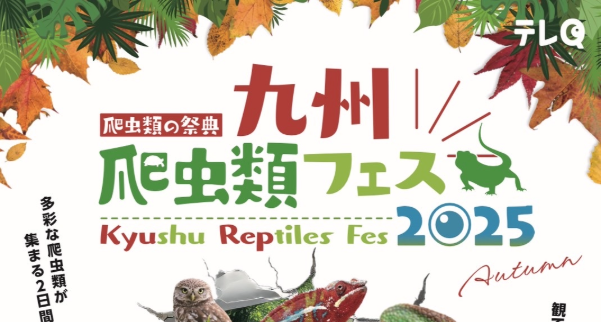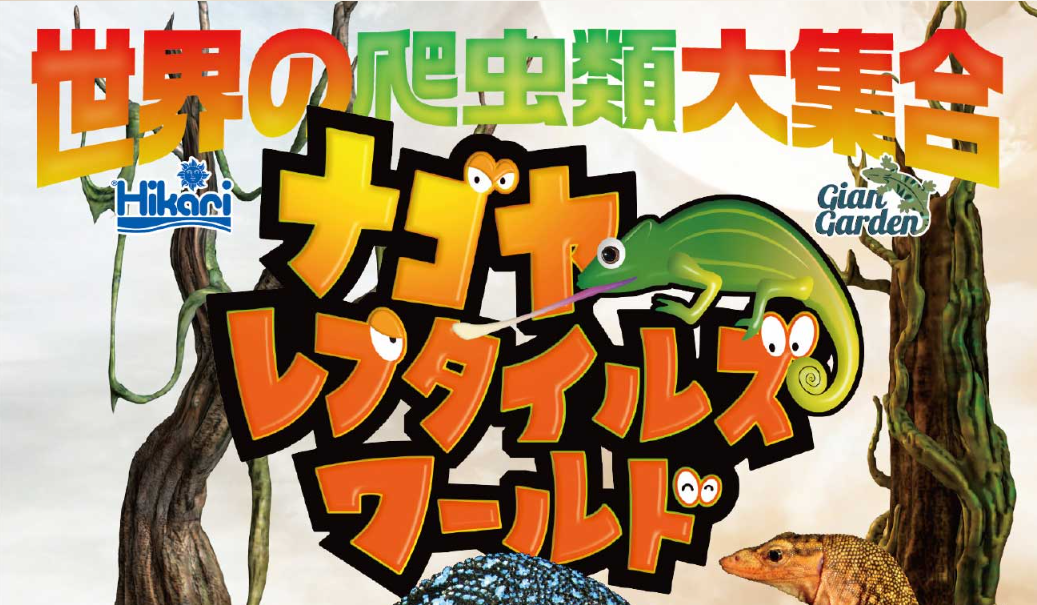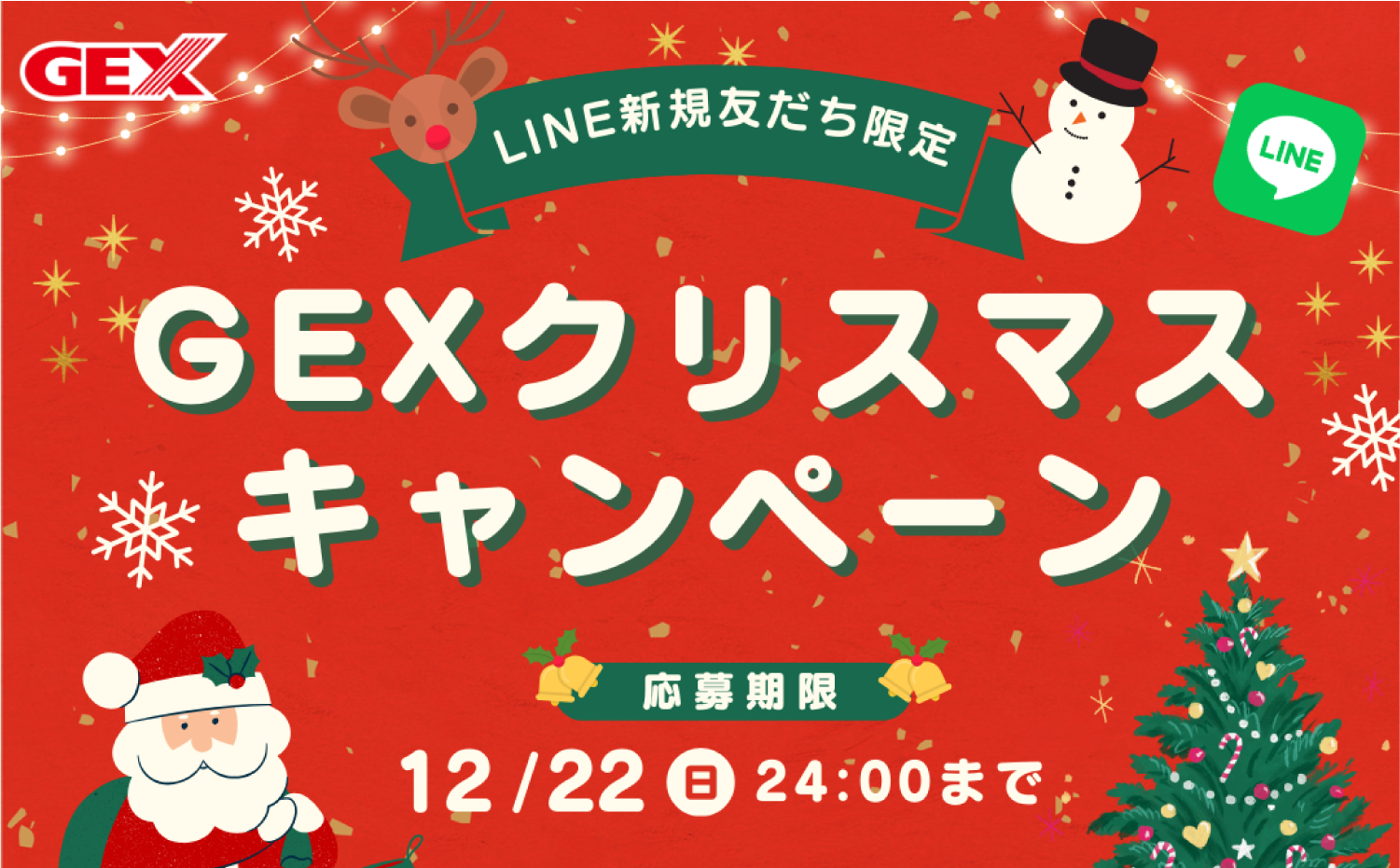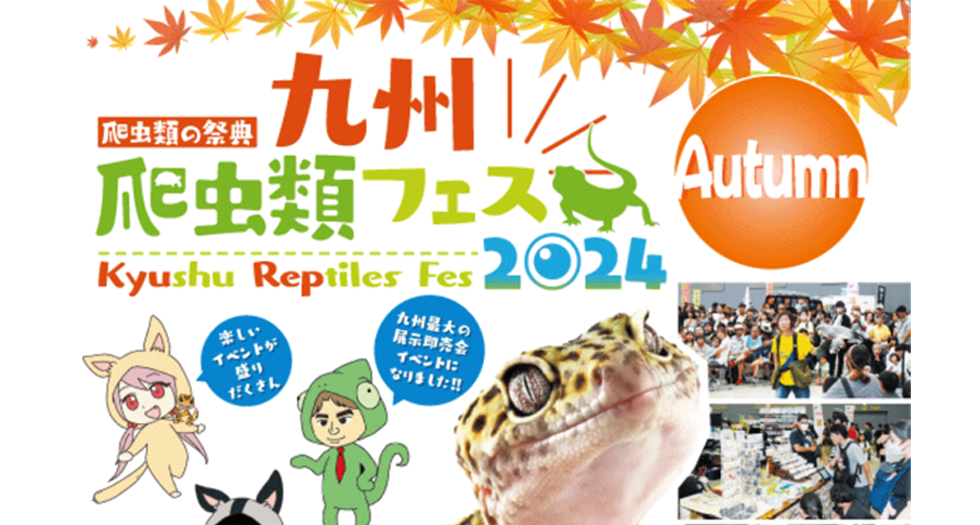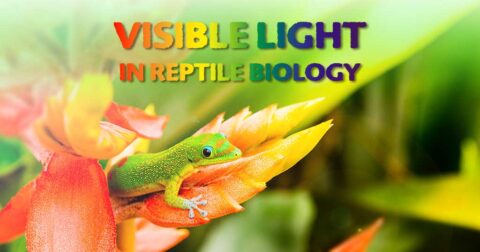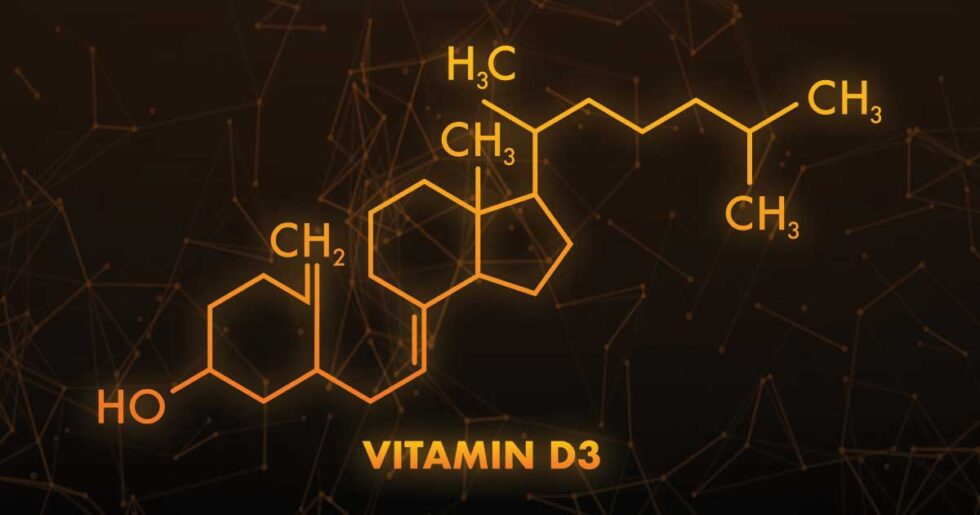豊かな自然と迫力ある海岸の崖に囲まれたレユニオン島。そこでひっそりと暮らすのは、小さく色鮮やかなマナパニーヒルヤモリ(Phelsuma inexpectata)です。
このヤモリは、レユニオン島だけに棲息する、とてもめずらしい種類です。人の手によって自然環境が変化したことにより、元々どこまで分布していたのかは、今ではよくわからなくなっています。
現在、マナパニーヒルヤモリは南海岸付近、海から100メートル以内の狭い範囲で小さな棲息地を点在させながら、この神秘的なヤモリは今日も力強く生きています。

マナパニーヒルヤモリ(Phelsuma inexpectata)
崖の上で生きる
レユニオン島の南東海岸沿いに位置する「ワイルド・サウス」は、ダイナミックな自然が広がるエリアです。玄武岩が連なる荒々しい海岸線、深い渓谷や森を縫うように流れる滝や川、そしてインド洋の力強い波がこの土地の個性を形づくっています。
この地域は島の他の場所より高温多湿で、サトウキビや果樹、マナパニーヒルヤモリなどの固有種の生存に欠かせない“ヴァコア”と呼ばれるタコノキの群生など、生命力あふれる熱帯植物が豊かに育っています。
この小さなヤモリが選ぶのは、緑で覆われた海沿いの崖。この景観はモーリシャス島の近縁種であるニシキヒルヤモリ(Phelsuma ornata)が暮らす環境とよく似ています。専門家によると、マナパニーヒルヤモリはかつてこの島の西海岸にも広く棲息していた可能性があるそうです。その証拠とされる骨や卵などの化石が発見されていますが、それが本当にこの種だったのかは、いまだはっきりしません。
現在の個体群動態の謎は、保全活動をより複雑にしています。どの個体群が純粋な在来種で、どの個体群が持ち込まれた外来種であるかの判断は困難です。この種は高い適応能力で、時には町の庭先などで繁殖することもあります。ペットとして持ち込まれたグループが根付いた例もあり、プティット・イルやサン・ジョセフといった町で現存する個体群が、本来この地にいたものか、後から加わったものか判別が難しい場面もあります。
高い適応能力にもかかわらず、近年の調査ではこの種の多くが棲息地を失っていることが明らかになっています。2008年から2010年にかけての観測の結果、いくつかの個体群が絶滅の危機に瀕しており、その多くはすでに姿を消している可能性が高いそうです。
それでも彼らは最大で海抜200メートルという多様な環境の中で、たくましく生きています。

南部レユニオンの崖沿いのタコノキ(Pandanus utilis)森林
マナパニーヒルヤモリの危機的な闘い
IUCNのレッドリストで「絶滅寸前」とされるマナパニーヒルヤモリは、まさに消滅の瀬戸際に立たされています。その存在が許されている棲息域は、わずか15平方キロメートル。しかもその中でさえ、ヤモリたちは点在する狭い“すみか”に分断されて暮らしています。この極端な断片化によって、遺伝的な多様性が保たれにくくなり、繁殖も難しくなるなど、種の存続は一層厳しい状況です。
レユニオン島の開発が進み、人々の活動が広がることで、かつて生きものたちを支えていた自然環境は年々失われています。森が切り拓かれ、海岸線の姿も変わり、ヤモリにとって大切な場所はどんどん減ってしまいました。その結果、彼らは限られた小さなエリアに追いやられ、餌や隠れ場所をめぐる競争が激化。さらに、病気や異常気象など予測できない出来事が、わずかに残った個体群への打撃となり、絶滅のリスクをいっそう高めています。

プティ・イル付近で交尾するマナパニーヒルヤモリのペア、レユニオン南部

Exo Terra
ブランドマネージャー

レユニオン島の南部海岸:マナパニーヒルヤモリの棲息地

タコノキ(Pandanus utilis)にいるマナパニーヒルヤモリ(Phelsuma inexpectata)

タコノキ(Pandanus utilis)の葉の上にいるマナパニーヒルヤモリ(Phelsuma inexpectata)